is-multitasking-really-efficient-pitfalls-to-watch-out-for「ながら作業」は本当に効率的?注意すべき落とし穴
-
株式会社REPRESENT(レプリゼント)ブログ「ながら作業」は本当に効率的?注意すべき落とし穴
ブログ
2025.11.7
「ながら作業」は本当に効率的?注意すべき落とし穴
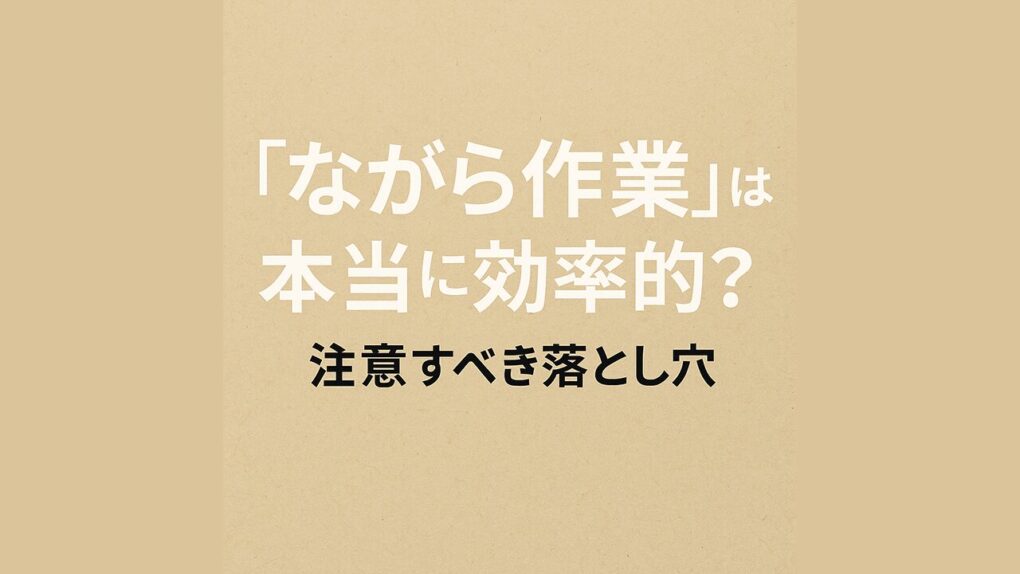
―脳科学が明かす“マルチタスクの錯覚”と集中力の真実―
マルチタスクこそ「効率的」だと思っていませんか?
音楽を聴きながら勉強、動画を流しながら資料作成、LINEを返しながら仕事。
現代人の多くは“ながら作業”を当たり前のように行っています。
「同時にいろいろこなせて時間の節約になる」と感じている人も多いでしょう。
しかし、心理学・神経科学の研究が示すのは、
「ながら作業=効率的」というのは大きな誤解だということです。
実は、脳は同時に複数のことを「処理しているように見えて」、
裏では高速でタスクを切り替えているだけなのです。
この「切り替えコスト」こそが、集中力を奪い、生産性を下げる最大の原因になります。
脳の仕組み:マルチタスクは“幻想”にすぎない
脳は“シングルタスク”が基本設計
スタンフォード大学の神経科学者クリフォード・ナス教授による研究では、
マルチタスクを習慣的に行う人ほど、注意力・記憶力・思考の切り替え能力が低下していることが明らかになりました。
脳の前頭前野は、論理的思考や判断を司る部位ですが、
複数の情報を同時処理するようにはできていません。
つまり、スマホ通知を見ながら資料を作るとき、
脳は「資料モード → 通知モード → 再び資料モード」と、
数秒単位で集中を切り替え続けているのです。
この切り替えのたびに、脳のエネルギー(グルコース)が消費され、
結果的に「短時間で集中力が枯渇する」状態になります。
ながら作業の“錯覚効率”に潜む3つの落とし穴
落とし穴①:作業スピードが最大40%低下する
ロンドン大学の調査によると、マルチタスクを行う人は
IQが一時的に10ポイント低下し、作業スピードも平均40%遅くなると報告されています。
一見テンポよく進んでいるように感じても、
実際は「切り替えの手間」で効率を失っているのです。
特に、スマホ通知・メールチェック・チャット返信などの短い割り込みタスクが、
脳の集中回復を妨げる最大の要因になります。
落とし穴②:ミスが増える・記憶に残らない
集中が途切れると、脳は情報を「短期記憶」にしか保持できません。
そのため、作業内容をすぐに忘れてしまい、再確認ややり直しが発生します。
例えば、文章を書きながらSNSをチェックすると、
文章構造や言葉の流れを何度も見失うことがありますよね。
これは、脳が同時に複数の思考を“保持できない”ためです。
落とし穴③:達成感が薄れ、疲労だけが残る
マルチタスク中は常に脳が“分散状態”にあるため、
どのタスクも中途半端に終わる感覚を生み出します。
しかも、常に切り替え刺激を求める習慣がつくと、
「ひとつのことに没頭する」能力自体が衰えるとまで言われています。
SNSを見ていないと落ち着かない、
静かな時間が退屈に感じる…というのもその一例です。
科学的に「ながら作業」をやめる3ステップ
ステップ①:タスクを“並列”ではなく“直列”で処理する
最も基本的な対策は、同時処理をやめて一列に並べることです。
実践法
- タスクを5〜10分単位で細分化(例:「資料作成」→「構成」「見出し」「本文」)
- ひとつ完了するたびに、次のタスクへ
- 「今やることリスト(ToDo)」を1本化しておく
このように順番を明確にすることで、脳の切り替え回数を減らし、
「やり切る快感」を得やすくなります。
ステップ②:環境を“強制的に集中モード”に変える
集中は意志よりも環境に左右されます。
ハーバード大学の研究では、誘惑を視界から消すだけで集中力が最大2倍に高まることが分かっています。
実践法
- スマホは机の上から“物理的に”離す
- 通知を一括オフにする(集中モード・おやすみモード)
- 音楽は“作業用BGM”ではなく、静音か環境音を選ぶ
- 複数タブを開かない。作業ウィンドウは常に1枚だけ。
「ながら作業」を防ぐ環境を作ることで、脳を“シングルタスクモード”に戻します。
ステップ③:集中と休憩をセットで設計する
人間の集中力は永続しません。
そのため、意識的に「集中→リセット」を繰り返すことが大切です。
おすすめリズム:「ポモドーロ・テクニック」
- 25分集中 → 5分休憩 × 4セット
- 4セットごとに15〜30分の長め休憩
- 休憩中はスマホ禁止。目を閉じる or 軽くストレッチ。
このリズムは、脳の“前頭前野”の疲労を防ぎ、
「集中を保ったまま1日を乗り切る」ための科学的手法として知られています。
「ながら作業」が許されるケースもある?
実は、すべてのながら作業が悪いわけではありません。
重要なのは「意識的か無意識的か」の違いです。
“自動化された作業”+“軽い刺激”はOK
例えば、
- 家事をしながら英語リスニング
- 通勤中にオーディオブック
- 散歩中にアイデアメモを録音
など、脳が無意識に処理できる作業+学びや発想は、
むしろ記憶定着を助けることがあります。
これは“デュアルタスク効果”と呼ばれ、
単調な動作にリズム刺激を与えることで、脳の活性化を促すことが分かっています。
ただし「意識を分散させる組み合わせ」はNG
逆に、
- SNSを見ながら勉強
- メールを返しながら資料作成
- 会議中に別案件を考える
といった“注意が必要な作業同士”は、脳が混乱を起こし、
どちらの質も落ちてしまいます。
まとめ:ながら作業の効率は「幻想」
| 比較項目 | シングルタスク | ながら作業 |
|---|---|---|
| 集中力 | 高い(没頭できる) | 分散しやすい |
| 作業速度 | 安定 | 一見速いが実際は遅い |
| ミス率 | 低い | 高い |
| 疲労感 | 少ない | 脳が消耗しやすい |
| 達成感 | 明確に得られる | 薄く、満足度が低い |
マルチタスクは「時間を増やす」どころか、
むしろ思考を分断し、集中を奪う最大の敵です。
まずは「ながら」をやめて、ひとつのことに全力を注ぐ時間を作る。
それだけで、あなたの1時間はこれまでの3倍価値ある時間に変わります。
まとめキャッチコピー
「ながら作業」で進んだ気になるのは、脳が“錯覚”しているだけ。
本当の効率は、“一度にひとつ”の中にある。
#集中力 #作業効率化 #脳科学 #時間術 #生産性向上 #ライフハック #学習効率 #仕事術 #自己啓発 #習慣化 #ながら作業 #モチベーションアップ #スマホ断ち




