habits-to-get-yourself-back-on-track-when-your-motivation-dropsモチベーションが下がったときの“立て直し習慣”
-
株式会社REPRESENT(レプリゼント)ブログモチベーションが下がったときの“立て直し習慣”
ブログ
2025.11.13
モチベーションが下がったときの“立て直し習慣”
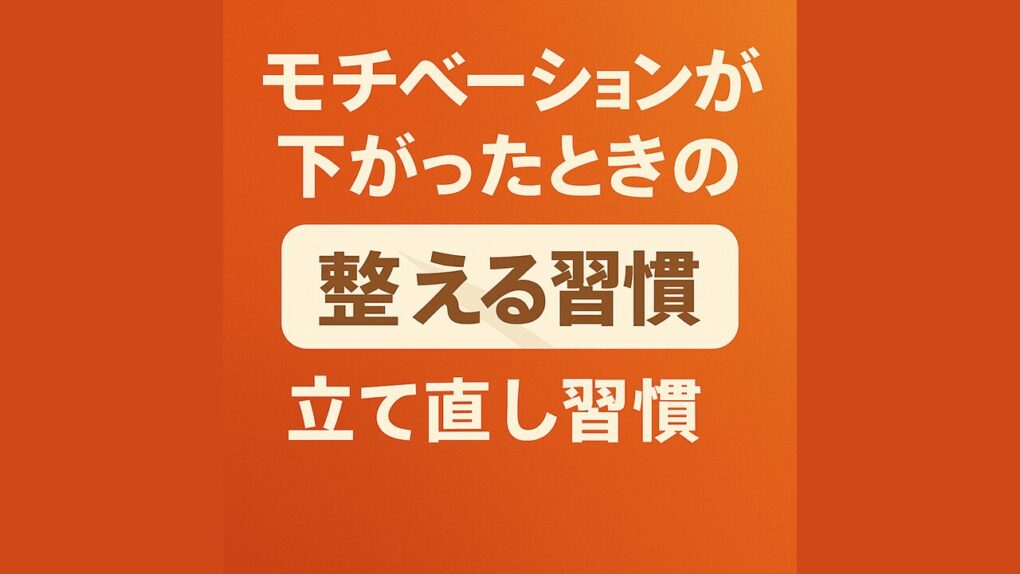
―やる気に頼らず、再び動き出すための心理学的アプローチ―
「やる気が出ない」は誰にでも起こる
どんなに意識が高い人でも、モチベーションが下がる時期はあります。
勉強、仕事、ダイエット、トレーニング…。
「続けたい」と思っていたはずなのに、
気づけばやる気が湧かず、何も手につかない。
そんなとき、多くの人は「自分は意思が弱い」と責めてしまいます。
しかし実は、やる気の波は脳の仕組みによって自然に起こるもの。
落ち込むのではなく、立て直す“習慣”を持っておくことが大切です。
この記事では、心理学と行動科学の観点から、
モチベーションが下がったときに使える「立て直しの習慣」を紹介します。
モチベーションが下がるのは“脳の防衛反応”
脳は「負担」を避けるようにできている
脳の基本原理は省エネです。
新しいこと・難しいこと・面倒なことに直面すると、
脳は「リスクが高い」と判断してブレーキをかけます。
その結果、「やる気が出ない」「疲れた」と感じるのです。
つまり、モチベーションが下がるのは自然な反応。
大事なのは、それを“長引かせない仕組み”を持つことです。
やる気の正体:「ドーパミン」と「報酬期待」
やる気=報酬を予測する脳の反応
モチベーションの源は、脳内物質ドーパミンです。
これは「何かを得られそう」と期待した瞬間に分泌され、
私たちに「やろう!」という意欲を与えます。
つまり、ドーパミンが出るのは「行動前」ではなく「期待したとき」。
報酬が遠すぎると分泌が減り、やる気も下がります。
ポイント
“結果”ではなく、“行動そのもの”に小さな報酬を設定することで、
モチベーションを再起動させることができます。
立て直し習慣①:「1分だけやる」
心理学では「作業興奮(ゼイガルニク効果)」という現象があります。
人は「やりかけのこと」が気になり、続けたくなる性質を持っています。
つまり、始めることさえできれば、自然に続けられるのです。
実践法
- 「1分だけ本を開く」
- 「パソコンを立ち上げる」
- 「英単語を1つだけ見る」
始めるハードルを下げることで、脳が“行動モード”に切り替わります。
1分行動でも、再起動のスイッチとして十分な効果があります。
立て直し習慣②:「“やる気を出す”のではなく“環境を整える”」
スタンフォード大学の行動科学者BJ・フォッグ博士は、
「行動は意志ではなく環境で決まる」と述べています。
やる気が出ないときは、意志力を使うよりも、
物理的な環境を“やるしかない状態”に変えるほうが効果的です。
実践法
- スマホを別の部屋に置く
- 机の上を整理して“勉強するしかない環境”を作る
- ストップウォッチを押して「5分間だけ集中」
環境を整えるだけで、脳は自動的に行動を始めやすくなります。
立て直し習慣③:「小さな達成感」を記録する
やる気を維持できる人の共通点は、「進んでいる感覚」を持っていること。
脳は達成感を感じると、ドーパミンが分泌され、再び行動を促します。
実践法
- カレンダーに「できた日」に○をつける
- アプリで「勉強時間」を可視化する
- SNSや日記で「今日の一歩」を記録する
人は“見える進歩”があると継続しやすくなります。
逆に、進歩が見えないとモチベーションが下がりやすい。
「見える仕組み」こそ、立て直しのカギです。
立て直し習慣④:「休む勇気」を持つ
モチベーションが下がる原因は、単なる怠けではなく脳の疲労である場合も多いです。
集中し続けると、前頭前野(思考や判断を司る部分)が疲弊し、
“何もしたくない”状態になります。
対策
- 30分作業+5分休憩(ポモドーロ・テクニック)
- 週1日は「何もしない日」をつくる
- スマホやSNSから一時的に離れる
休むことは“立て直しの一部”。
回復した脳は、以前よりも高い集中力を発揮します。
立て直し習慣⑤:「モチベーション日記」をつける
心理学者ショーン・エイカー氏(ハーバード大学)は、
ポジティブ心理学の研究で「感情の記録」が習慣維持に効果的だと証明しました。
やる気が下がっているときほど、自分の感情を可視化することが重要です。
書き方例
- 「今日はやる気が出なかった理由」
- 「それでもできた小さなこと」
- 「明日は1つだけこれをやる」
書くことで思考が整理され、「できない自分」ではなく「向き合う自分」に意識が変わります。
たとえ短い文章でも、脳への“再起動スイッチ”になります。
立て直し習慣⑥:「目的」を再確認する
行動心理学では、やる気が下がる最大の原因は「目的の希薄化」とされています。
つまり、“なぜそれをやるのか”を見失うとモチベーションは落ちるということ。
実践法
- 「なぜ始めたのか」を紙に書き出す
- 「それが叶ったとき、自分はどう変わるか」を想像する
- 「小さなゴール」を再設定して達成感を取り戻す
目的を“再接続”することで、行動の意味が明確になり、やる気が戻ります。
モチベーションが戻る「タイミング」を知る
実は、モチベーションは一定ではなく波のように変動します。
研究によると、人間の集中力ややる気は90分周期で上下しており、
これを「ウルトラディアンリズム」と呼びます。
したがって、モチベーションが下がったら、
「今は低潮期だから仕方ない」と捉えてOK。
そして次の上昇期(90分後〜翌日)に“再起動”する。
「無理に頑張らず、波を見極める」のが長期的な継続のコツです。
「行動できない自分」ではなく「立て直せる自分」になる
モチベーションが落ちるのは悪いことではありません。
むしろ、「どう立て直すか」を知っている人ほど、長く続ける力を持っています。
小さな習慣でもいい。
“止まっても、戻れる自分”を育てることが、真の継続力です。
まとめ:「モチベーション管理」ではなく「リズム設計」
| 状況 | 立て直し習慣 |
|---|---|
| やる気が出ない | 1分だけ行動してスイッチを入れる |
| 集中できない | 環境を変える・スマホを遠ざける |
| 成果が見えない | 記録をつけて進捗を“見える化” |
| 疲れている | 思い切って休む・脳をリセット |
| 目的を見失った | “なぜ始めたか”を書き出して再確認 |
モチベーションを「上げよう」とするのではなく、
「戻せる仕組み」を持つことが、継続する人の思考法です。
キャッチコピー
「やる気は待つものではなく、整えるもの。」
―立て直せる人が、続けられる人になる。
#モチベーションアップ #立て直し習慣 #やる気が出ない時 #メンタルケア #自己啓発 #行動心理学 #継続力 #ライフハック #時間術 #ストレスマネジメント #ポジティブ思考 #心の整え方 #モチベ管理 #習慣化 #メンタルヘルス




