ebbinghauss-forgetting-curve忘れない勉強法:エビングハウスの忘却曲線を活かす
-
株式会社REPRESENT(レプリゼント)ブログ忘れない勉強法:エビングハウスの忘却曲線を活かす
ブログ
2025.9.12
忘れない勉強法:エビングハウスの忘却曲線を活かす
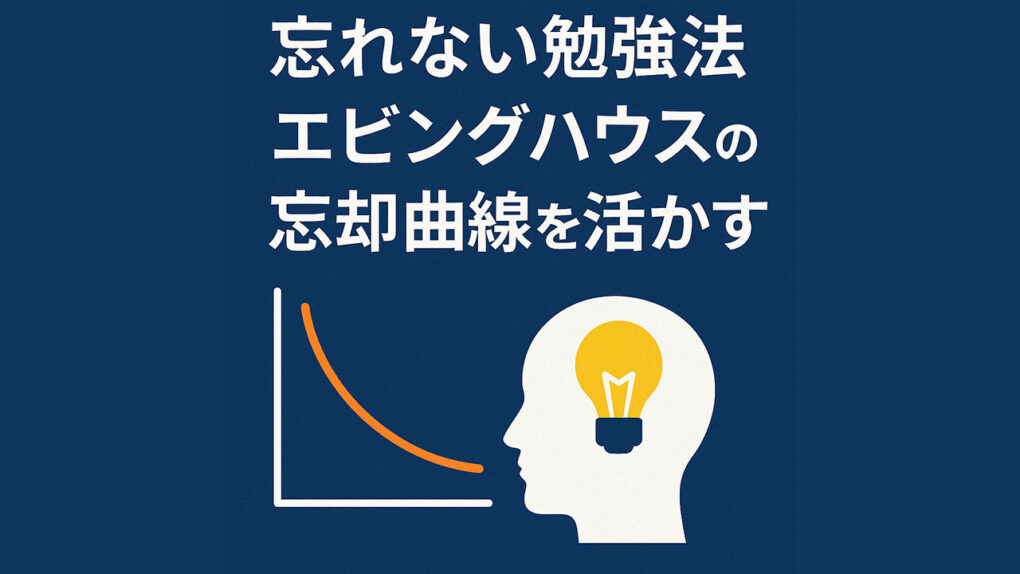
はじめに:なぜ人は忘れるのか?
「昨日覚えたはずなのに、もう忘れている」
誰しも経験のあるこの現象は、人間の脳の仕組みによるものです。
ドイツの心理学者 ヘルマン・エビングハウス が提唱した「忘却曲線」によれば、
人は学んだ内容の半分以上を1日以内に忘れてしまうとされています。
この研究は19世紀に行われたものですが、現代の学習法にも大きな示唆を与えており、
特に「復習のタイミング」の重要性を教えてくれます。
エビングハウスの忘却曲線とは?
1. 定義
忘却曲線とは「人が学んだことをどれくらいの速度で忘れていくか」をグラフ化したものです。
エビングハウスの実験では、人は無意味な音節を覚えてどのくらい記憶が残るかを調べました。
その結果
- 20分後:42%を忘れる
- 1時間後:56%を忘れる
- 1日後:74%を忘れる
- 1週間後:77%を忘れる
- 1か月後:79%を忘れる
つまり、最初の1日で一気に忘却が進むのです。
忘却曲線を活かす「復習の黄金タイミング」
忘却曲線が示すのは「人は忘れる生き物である」という現実です。
しかし逆に言えば、適切なタイミングで復習すれば、記憶を長期保存できるということです。
復習の目安
- 1回目の復習:学習後24時間以内
- 2回目の復習:学習後1週間以内
- 3回目の復習:学習後1か月以内
このサイクルで復習を重ねると、記憶の定着率は大幅に向上します。
忘却曲線を応用した勉強法
スペースド・リピティション(間隔反復)
忘却曲線を応用した学習法として有名なのが「スペースド・リピティション」です。
学習内容を忘れかけるタイミングで繰り返し復習する方法で、語学学習や資格試験勉強に広く使われています。
代表例は「Anki」や「Duolingo」のようなアプリで、自動的に復習間隔を調整してくれます。
アクティブリコール(能動的想起)
ただ読み返すのではなく、自分の記憶から答えを引き出す練習をすることで定着率が上がります。
例:
- 問題集を解く
- ノートを閉じて思い出す
- 他人に説明する
思い出そうとする行為そのものが脳に刺激を与え、記憶を強化します。
ランダム復習
常に同じ順番で復習するのではなく、シャッフルして出題する方法です。
脳に「新鮮さ」を与えることで記憶が強固になります。
忘却曲線×日常習慣の工夫
朝と夜の使い分け
- 朝:新しいことを学ぶ時間に最適(脳がリフレッシュしているため)
- 夜:復習の時間に最適(寝る前に復習すると記憶が定着しやすい)
マイクロ学習
一気に長時間学習するより、短時間を複数回に分ける方が効果的です。
例:通勤中に単語帳を5分だけ開く。
デジタルツールの活用
Googleカレンダーで「復習リマインダー」を設定するなど、ツールに習慣化を助けてもらう。
忘却曲線を克服する実践モデル
モデルA:語学学習
- 新しい単語を30個覚える
- 24時間以内に再チェック
- 1週間後にテスト形式で確認
- 1か月後に文章の中で使ってみる
モデルB:資格試験
- テキストを1章読む
- その日の夜に問題演習
- 1週間後に模擬テスト
- 1か月後に総復習
「忘れる前に思い出す」仕組みが肝心です。
忘却曲線と組み合わせたい心理学テクニック
テスト効果
「学習=インプット」だけではなく、「テスト=アウトプット」で記憶が強化される。
メタ認知
「自分がどこを覚えていて、どこを忘れているか」を把握する力。学習ログで弱点を明確化することが有効。
場所の記憶
学んだ場所や状況と記憶が結びつくことがある(コンテキスト効果)。
勉強場所を変えてみると記憶が強くなる。
まとめ
忘却曲線を前提に学習計画を立てることで、効率的かつ長期的な成果が得られる
エビングハウスの忘却曲線は「人はすぐに忘れる」という事実を示す
しかし、適切なタイミングで復習すれば記憶は定着する
スペースド・リピティションやアクティブリコールが効果的
朝は新しい学習、夜は復習という使い分けも有効




