how-to-get-started-with-data-driven-marketing-what-is-the-strategy-that-uses-numbers-to-get-resultsデータドリブンなマーケティング運用の始め方:数字を武器に成果を出す戦略とは?
-
株式会社REPRESENT(レプリゼント)ブログデータドリブンなマーケティング運用の始め方:数字を武器に成果を出す戦略とは?
ブログ
2025.7.28
データドリブンなマーケティング運用の始め方:数字を武器に成果を出す戦略とは?
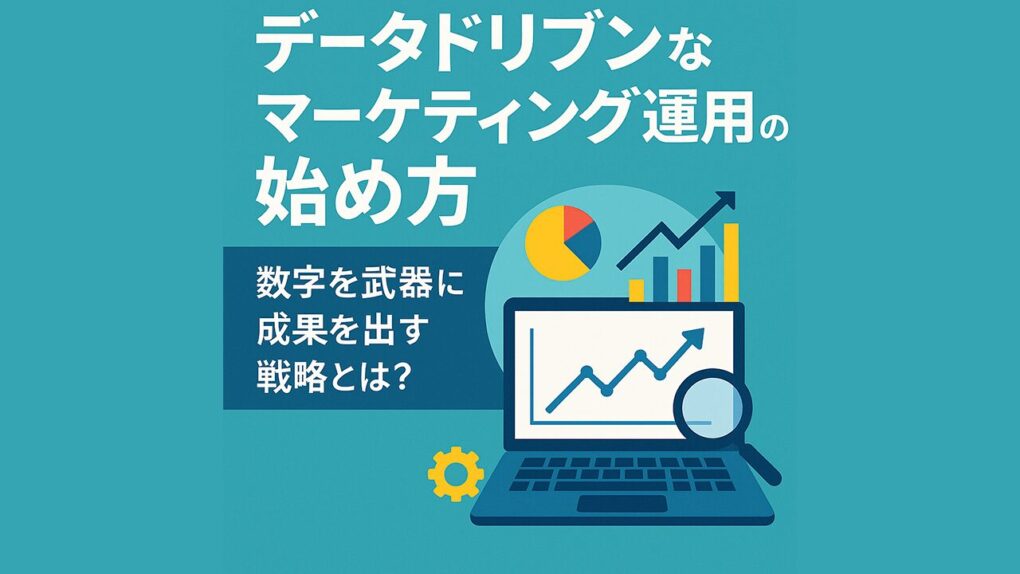
「なんとなく効果がありそう」で判断していませんか?
現代のマーケティングでは、勘や経験よりも“データ”が意思決定の核となっています。
とはいえ、「データドリブンって難しそう」「ツールが多すぎて何から始めれば…」
という声も少なくありません。
この記事では、これからデータドリブンマーケティングを導入・実践したい企業や
マーケターに向けて、基礎からステップごとに解説します。
データドリブンマーケティングとは?
定義
データドリブン(Data Driven)とは、「データを根拠に意思決定を行う」考え方。
マーケティングにおいては、アクセス解析、購買履歴、広告データ、SNS反応などを活用し、
定量的な根拠に基づいて戦略や施策を立案・実行することを意味します。
なぜ今、注目されているのか?
- Cookie規制により、ファーストパーティデータの価値が急上昇
- 広告費の最適化ニーズ
- 個別最適化(パーソナライズ)の重要性
- AIやBIツールの進化により、活用しやすくなった
データドリブン運用で得られる3つのメリット
① 判断の精度が上がる
「どの広告が効いているか」「どのコンテンツがCVに寄与しているか」など、
感覚に頼らず正確な判断が可能に。
② 無駄な施策が減る
数字で効果を測るため、「やって終わり」「続ける理由がない」施策が可視化され、
費用対効果が高まる。
③ チームでの共通認識がとれる
KPIや指標が共有されていれば、チーム全体が同じ目的に向かって動きやすくなる。
データドリブンマーケティング運用の始め方【7ステップ】
ステップ①:目的を明確にする
まず「何のためにデータを使うのか」を定義しましょう。
例
- 広告の費用対効果を改善したい
- 顧客離脱の原因を知りたい
- LTVを高めたい
- コンテンツの反応率を測りたい
「KGI(最終目標)」と「KPI(中間指標)」を設定しておくと、判断の軸がぶれません。
ステップ②:活用可能なデータを洗い出す
以下のような社内データが使えるかを棚卸ししましょう。
| データ種別 | 具体例 |
|---|---|
| ウェブ解析 | Google Analytics、GA4、ヒートマップ、ページビュー、滞在時間 |
| 広告データ | Google Ads、Meta広告のCPC、CTR、CVR、ROASなど |
| CRMデータ | 顧客属性、購買履歴、LTV、チャーン率、問い合わせ履歴 |
| SNSデータ | いいね数、リーチ数、保存数、コメント分析など |
| アンケート | 満足度、NPS、理由付きの自由回答 |
ステップ③:KPI設計をする
データを収集するだけでは意味がありません。「何を見て、どう判断するのか」が重要です。
KPIの例
- LPのコンバージョン率(CVR)を3%→5%に改善
- 顧客の平均LTVを1.2倍にする
- 直帰率を30%以下に抑える
- SNSのエンゲージメント率を2倍にする
KPIは、「目的に直結する数値」にするのがポイントです。
ステップ④:ツールを整備する
初心者でも導入しやすいおすすめツール:
| 目的 | ツール例 |
|---|---|
| ウェブ解析 | GA4(Google Analytics 4)、Clarity、Hotjar |
| ダッシュボード可視化 | Looker Studio、Tableau、Power BI |
| CRM・メール連携 | HubSpot、Salesforce、KARTE、Kintone |
| MA(自動化) | Marketo、b→dash、List Finder |
| SNS管理 | SocialDog、Hootsuite、Postoplan |
※無料から始められるものも多いため、まずは1つに絞って運用するのがおすすめ。
ステップ⑤:ダッシュボードを作成する
Excelやスプレッドシートでの手動集計も可能ですが、Looker StudioやTableauを使えば、
リアルタイムで自動更新される可視化が可能です。
可視化のコツ
- 「誰が」「いつ」「何のために」見るのかを明確に
- 上位5コンテンツ・地域別CV・流入元別など、ストーリー性を意識
- シンプルに1画面で完結する構成に
ステップ⑥:仮説を立てて小さくテスト
データを見たら、必ずアクションに繋げましょう。
例
- 離脱率の高いページがある → CTA配置を変えてみる
- モバイルからのCVが少ない → モバイル最適化を実施
- メルマガの開封率が下がっている → タイトルA/Bテストを実行
データ→仮説→テスト→改善、のPDCAが基本サイクルです。
ステップ⑦:定例でレビューし、改善を継続する
週次・月次などで「データレビュー会」を設けると、チーム全体の意識も高まります。
見るべきポイント
- 予測と実績の差(差異分析)
- KPI達成度
- 次のアクション案
ここで出たアイデアを次回の施策に反映すれば、データ活用が「使い捨て」にならず継続できます。
よくある失敗とその対策
| 失敗パターン | 対策 |
|---|---|
| データが多すぎて混乱 | 見る指標を3つ程度に絞る。シンプルなKPIを設定 |
| データが社内に分散 | GoogleスプレッドシートやBIで一元管理する体制を構築 |
| 数字は見ているがアクションにつながらない | 定例で改善提案まで行うルールを設ける |
| ツールに投資しすぎる | 無料・トライアルからスタートし、小さく始めて評価 |
まとめ:小さなデータ活用から“成果”が生まれる
データドリブンな運用は、最初から完璧にやる必要はありません。むしろ、
「小さな成果を積み重ねて、意思決定の質を上げていくこと」が重要です。
最後に、まず実践すべき3ステップをおさらいします。
- 目的とKPIを決める
- 手元のデータを1つ使って仮説を立てる
- 結果を見て、次の改善を考える
このサイクルを回すことで、あなたのマーケティングは“数字に強く”、
“説得力のある”ものへと進化します。




