rather-than-taking-notes-train-your-ability-to-summarizeノートを取るより“まとめる力”を鍛えよう
-
株式会社REPRESENT(レプリゼント)ブログノートを取るより“まとめる力”を鍛えよう
ブログ
2025.10.20
ノートを取るより“まとめる力”を鍛えよう
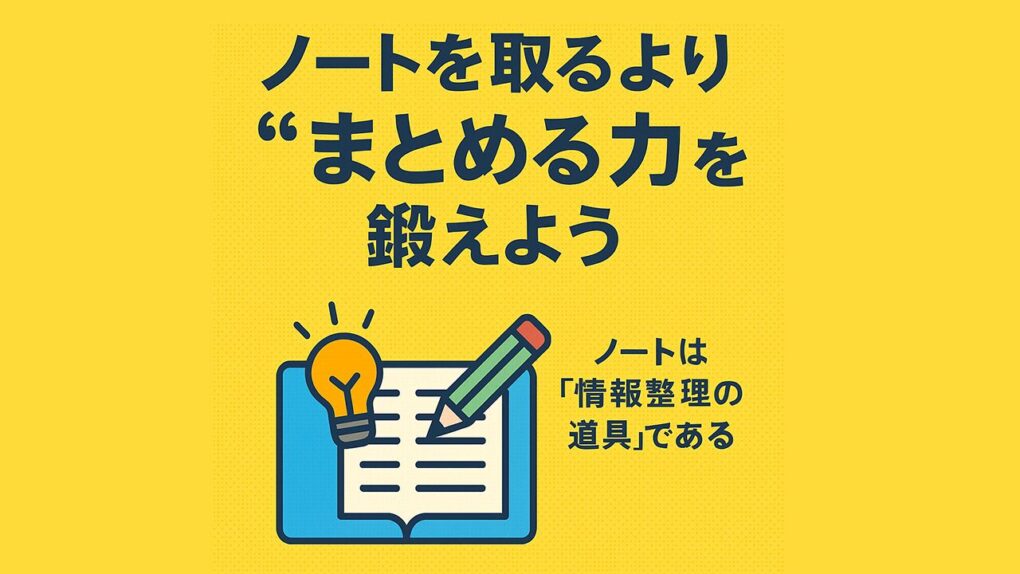
──「書く」より「整理する」で学びが深まる
はじめに:「きれいなノート」より「使えるノート」を
「授業中、一生懸命ノートを取ったのに、後から見返してもよくわからない」
「書いた満足感だけで終わってしまう」
…そんな経験、ありませんか?
多くの人が「ノートを取る=勉強している」と思いがちですが、
実際には “まとめ方”が学習の質を左右する のです。
情報を「きれいに写すこと」が目的になってしまうと、学びは“受け身”のまま。
一方で、自分の言葉でまとめる力を鍛えると、
理解力・記憶力・応用力が格段にアップします。
この記事では、“まとめる力”の重要性と、その鍛え方を具体的に紹介します。
「書く」と「まとめる」は別の行為
まず理解しておきたいのは、ノートを取る=情報の記録
ノートをまとめる=情報の整理・再構築という違いです。
ノートを取る=“情報のコピー”
講義や本の内容を、そのまま写す行為。
一見学んでいるように見えて、実は「理解の浅い状態」で止まっています。
まとめる=“情報の変換”
自分の頭の中で咀嚼し、再構成するプロセス。
これは単なる作業ではなく、思考の訓練でもあります。
情報を「理解している人」ほど、短く・わかりやすく・自分の言葉で説明できる。
“まとめる力”がもたらす3つの学習効果
① 理解が深まる(構造的に考える力)
まとめる過程では、「何が重要か」「なぜそうなるか」を考えます。
これが自然と「構造的思考」を鍛えます。
例
歴史を丸暗記 → 「原因→結果→影響」という因果で整理
数学の公式 → 「何を求めるための式か」を言葉で説明
② 記憶に残りやすい(再整理で長期記憶化)
心理学の研究では、自分で要約した情報は記憶保持率が3倍になるといわれています。
“自分の言葉”に変換することで、脳が「これは大事」と判断するのです。
③ 応用力が高まる(転用の思考)
まとめる力があると、「別のテーマに置き換える」ことが得意になります。
つまり、他分野の知識と結びつけて使える力がつきます。
知識を「使える」人は、理解より“整理”が上手。
上手な「まとめノート」の作り方
それでは、実際に“まとめる力”を鍛えるノート術を紹介します。
ステップ1:情報を3段階で整理する
ノートを取るときは、「事実」「理由」「自分の考え」の3層で書くのが効果的です。
| 段階 | 内容 | 書き方例 |
|---|---|---|
| ① 事実 | 教材・講義の内容 | 「AはBの影響でCになった」 |
| ② 理由 | なぜそうなったか | 「Cになったのは〇〇が原因」 |
| ③ 自分の考え | どう感じたか・応用 | 「これは自分の仕事にも使える」 |
この3層構造で整理することで、理解が一気に深まります。
ステップ2:キーワードを中心にまとめる
文章ではなく、キーワード+矢印+図解でつなぐのがコツ。
ノートは“読むもの”ではなく“見るもの”に変えると、復習が速くなります。
例:
原因 → 出来事 → 結果
↑ ↓
背景 影響
ステップ3:「人に説明するノート」を意識
“他人に教える前提”でまとめると、説明力と理解力が爆発的に伸びます。
ポイントは
- 5分で説明できる量に絞る
- 難しい言葉を使わない
- 自分の言葉で書く
“説明できる=理解できている”のサイン。
「まとめノート」を作るタイミングと頻度
まとめるタイミングを間違えると、効率が落ちてしまいます。
おすすめは、以下のサイクルです
| タイミング | 目的 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 当日夜 | 記憶の定着 | 10〜15分 |
| 翌日 | 構造の整理 | 20分 |
| 週末 | 全体の再構築 | 30分〜1時間 |
“まとめる時間”を学習計画に組み込むことが重要。
勉強=覚える時間+整理する時間 と考えましょう。
デジタルツールで“まとめ力”を伸ばす
紙のノートだけでなく、デジタルツールを活用するとさらに効率的です。
おすすめアプリ
| ツール | 特徴 |
|---|---|
| Notion | テキスト・画像・リンクを整理できる万能ノート |
| Miro | マインドマップや図解に最適 |
| Googleスライド | 見せるまとめを作るのに向く |
| Obsidian | 知識をつなげる「リンク思考ノート」向き |
デジタルなら、再編集・再構成が簡単。
つまり、考えながらアップデートできる“生きたノート”になります。
「まとめ方」を意識した復習法
ただ見返すだけではなく、“自分に説明する復習”を意識しましょう。
リフレクション3ステップ
見返す(事実を確認)
まとめ直す(構造化)
話す(人に説明 or 音読)
このサイクルで、「わかる → できる」に変わります。
「まとめる力」を育てる習慣3つ
① “1日1テーマ”を簡潔にまとめる
1日の終わりに「今日学んだこと」を3行で書き出すだけでもOK。
→ 情報圧縮の筋トレになります。
② “なぜ?”を3回繰り返す
まとめるときに、「なぜそうなる?」を3回問い直すと、思考が深まります。
(トヨタ式“5 Whys”にも通じる方法)
③ “図で説明する”練習をする
言葉だけでなく、矢印・箱・線で構造を表すと理解が格段に深まります。
「図解力=まとめ力の上級形」。
“まとめる力”が仕事・人生でも役立つ理由
このスキルは、学生だけでなく社会人にも必要不可欠です。
- 上司への報告書が要点を押さえられる
- 企画書が短くても伝わる
- プレゼンが“理解される構成”になる
つまり、「情報を短く、わかりやすく整理する力」=社会で最も価値あるスキルなんです。
まとめ:ノートは「情報整理の道具」である
| 学習タイプ | 特徴 | 改善ポイント |
|---|---|---|
| ただ写す | 情報が多くて理解が浅い | 自分の言葉にする |
| まとめる | 情報が整理されて使える | 因果や関係性を意識 |
| 教える | 一番理解が深い | 他人に伝える前提で作る |
終わりに
ノートをきれいに取るよりも、どう“整理して伝えられるか”を意識することが学びの本質です。
「何を書いたか」より「どうつながったか」。
その思考を鍛えることが、“まとめる力”の第一歩です。
今日から、ノートの目的を“写す”から“整理する”へ変えてみませんか?




